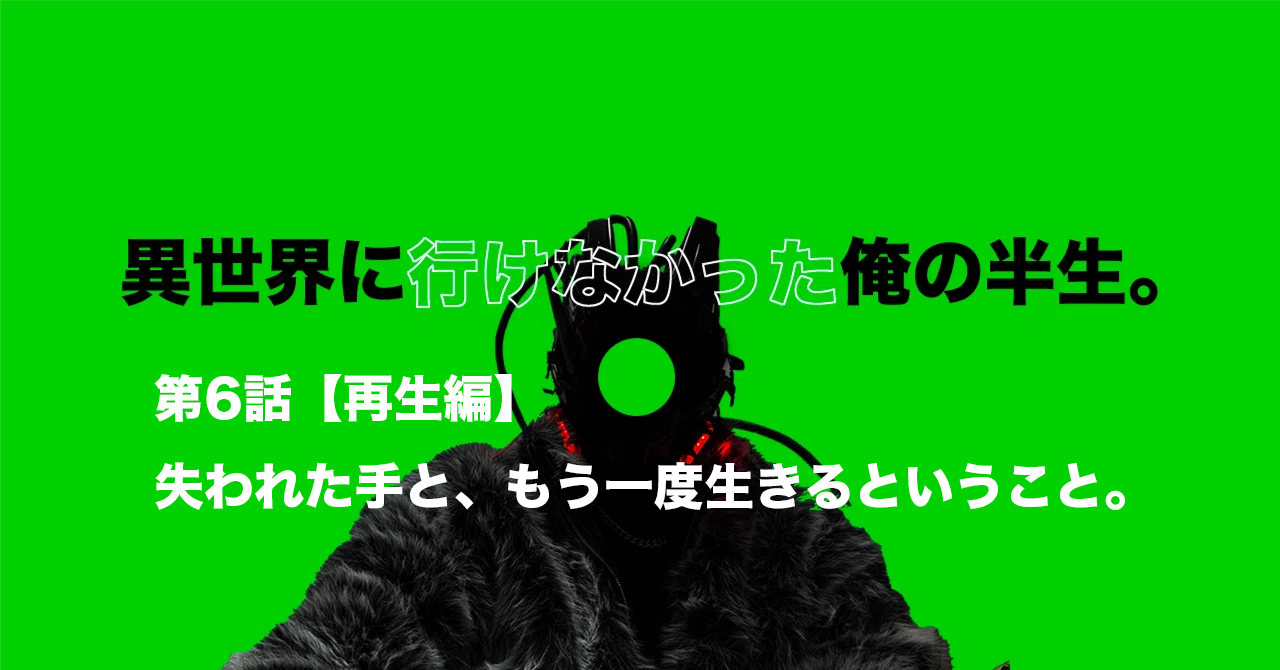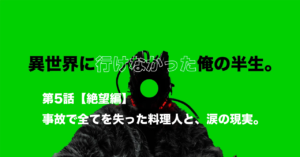▶ 前回(第5話)はこちら
事故で両腕の自由を失い、料理人としての未来が途絶えた主人公。
病院での絶望、友人の死、オヤッサンとの別れを経験しながら、
ただ“生きる”ことだけを支えに入院生活を続けた。
その先に何が残るのかも分からないまま、時間だけが進んでいく。
第5話 握れなくなった手の先で
▶︎ 最初から順番に読む
退院までの静かな時間
退院までにさらに3か月かかった。
最初の頃は、毎日のように誰かが見舞いに来てくれていたけれど、
時間が経つにつれて、だんだん人は少なくなっていった。
それでも母と妹だけは、ほぼ毎日顔を見せてくれたんだ。
父親は……たまにね。
腕は少しずつではあるものの、動くようになってきた。
当初はトイレにも行けなかったけれど、
自分で起き上がって多少の作業はできるようになった。
手先を使う細かい作業はまだ無理だけど、
それでも、腕そのものはまだ生きてるって感覚は確かにあった。
「料理は……無理だな」
自分に言い聞かせるように、ぽつりとつぶやいた。
それでも、自分で風呂に入れるようになった時、久しぶりに「俺、生きてるな」と思えたよ。
週に二回の入浴が本当に楽しみだった。
実家に帰り、家族と向き合う
そしてついに来た退院の日。
待ちに待った退院の日。
外の空気を吸った瞬間思わず笑っちゃったんだ。
ホント、「娑婆(しゃば)の空気がうまいぜ」ってね。
入院したことがある人ならわかるだろうけど、入院生活って本当に退屈なんだよ。
さて、どこに帰るか。
住んでいたアパートは保険と傷病手当金でなんとか借り続けていたけれど、
仕事もない今となっては、もう引き払うべきだろう。
そう思って、俺は実家に帰ることにした。
久々に足を踏み入れた実家。
あの荒れ果てた雰囲気は無くなっていた。
俺の退院にあわせて休みを取ってくれた父、母、妹。
久々にここで家族全員と顔を合わせた気がする。
「おかえり。よく頑張ったね」
母のその一言で、少し泣きそうになった。
「少し家でのんびりしておけ。何も気にするな」
父が言った。
亡くなった友人の家へ──謝罪と現実
──俺がまず最初にやらなければならないこと。
それは、亡くなった友人の家族への謝罪だ。
運転していなかったとはいえ、あの日、遊びに誘ったのは俺だ。
責任の一端は間違いなくある。
まず、ご両親とご兄弟に謝りたい。
そして、「許されたい」というずるい気持ちも、心のどこかにあったように思う。
友人の家を訪ね、俺の名前を伝えた瞬間、場の空気が変わった。
重く、冷たい空気。
言葉が出ない。
仏壇の前に飾られた友人の写真。
その笑顔を見たとき、ようやく実感した。
──もう、いないんだ。
「ごめん……」
その言葉だけを搾り出した。
ご両親は静かにうなずいた。
「いったい何が起きたのか」
ご両親に問われ、包み隠さず全てを話した。
そして、帰り際に言われた。
「もう、この家には来ないでほしい」
俺の顔を見るたびに、思い出してしまうから、と。
胸の奥がすうっと冷たく沈んでいった。
許しをもらえたのかどうかもわからないまま、
ただ、玄関先で何度も、何度も頭を下げ続けた。
自分が親となった今、あの時のご両親の気持ちが痛いほど理解できる。
あの日を思い出すと、今でも胸が締めつけられる。
・
・
・
手先を取り戻すための、長い戦い
仕事を探す前に、まずは体をなんとかしなきゃな。
折り紙を折ったり、リリアンを結ったり、ミサンガを作ったり。
手先の感覚を少しでも戻そうと、それまで一度もやったことのないことを、ひたすらやった。
毎日、飽きもせず。
紙の折り目が少しでもズレると、やり直し。
指先がちょっとでも思い通りに動くことが嬉しかった。
数週間も経つと、新しい生活にも慣れてくる。
そして――指先は、思っていた以上に回復の兆しを見せていた。
若いって、ほんとすごいよね。
折り紙もミサンガも、どんどん上達していく。
これって売り物になるんじゃ?と勘違いするレベルまで上手くなった。
両手両足は自分で作ったミサンガだらけ。
部屋の中には、誰のためのものかわからない大きな千羽鶴。
失った料理が家族をつなぎ直す
そうこうしているうちに、ふと、思ったんだよね。
「なんか料理したいな」
母も妹も、俺の作った料理を食べたがっていた。
だったら、毎日のご飯は俺が作るか。
どうせ無職だし、細かい作業がなければ、何か作れるだろう。
母が仕事から帰ってくると、二人でスーパーに行った。
「お金は気にしないで。美味しいものが食べたいの」
そう言われたら、料理人の血が騒ぐってもの。
その日から時には和食、時には中華、時には洋食。
いろんな料理を作った。
ただ――千切りや微塵切り。
包丁を使う作業だけは怖かった。
包丁を持つ手が震える。
慎重に、慎重に。
いや、無理だ。
野菜の刻みにはフードプロセッサーを使うことにした。
これ、俺が切るより細いんじゃないか?
それでも作った料理は評判がよかった。
気づくと、「なんか最近、晩ごはんが楽しみになった」
と、妹が仕事から早く帰るようになった。
夕食時は母・妹・俺の三人で笑いながら食事をし、
お酒も一緒に飲むようになった。
俺は調子に乗って、カクテルを勉強した。
せっかくだから、食卓もバーみたいに楽しくしてやろうと思ったんだ。
ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、ウイスキー。
リキュールもいろいろ揃えた。
ブルーキュラソーにアマレット、カンパリ、ベルモット。
本を片手に夜な夜な練習。
もう一度ひとつになる
そんなある日、
「あの」父親が家に早く帰ってくるようになったんだ。
「みんなが楽しそうだから、俺も仲間に入れてほしかった」
そう言われて、少し驚いた。
母は苦笑いしてたけど、悪い気はしなかったよ。
気づけば、家族みんなで食卓を囲んでいたんだよね。
こんなの、小学生の頃…団地に住んでいた時以来だ。
「ありがとね」
母が言った。
俺は照れくさくて、笑いながら答えた。
「ま、無職だし、これくらいしないとね」
あの頃の暗闇が嘘みたいに
家の中は穏やかで、あたたかかった。
次回
第7話 ゆっくり動き出した心の音に続く
動きを取り戻しつつある手とは裏腹に、心はまだ前に進めない。
それでも、小さな挑戦と出会いが、主人公を次の世界へ押し出していく。
再就職への一歩が、静かに始まる。
言葉の余韻を、もし感じたなら
ツギクルに参加しています。
もし、私のエッセイに感じたものがあったら、クリック頂けると幸いです。
コメント欄はありませんが、
X(旧Twitter)でそっと教えてください。
あなたの言葉が、次の物語の力になります。
▶ @atch-k
異世界に行けなかった俺の半生。シリーズ
▶︎ 最初から順番に読む
- 家庭崩壊、教育虐待、家出──壊れた家族の中で、それでも“生き直そう”とした少年の原点の物語。
第1話 壊れた夜の匂い - 海外で見た自由と孤独――家庭崩壊から逃げた少年が、母との絆を取り戻すまでの再生記。
第2話 海の向こうで呼吸した日 - ― 包丁と涙で刻んだ“下積み時代” ―
第3話 包丁の重さを知った朝 - ― 包丁と向き合い、職人としての道を歩き始めた ―
第4話 魚を捌く音だけが響いた - ― 包丁を握れなくなった日、全てが終わったと思った ―
第5話 握れなくなった手の先で - ― 動かない手を見つめながら、もう一度生き直そうと思った ―
第6話 動かない手と沈黙の部屋 - ― リハビリで手は動くようになった。けど、心はまだ止まってた ―
第7話 ゆっくり動き出した心の音 - ― 社会復帰した職場は、いじめと理不尽が渦巻く“地獄の入口”だった。 ―
第8話 社会の入口に立った朝 - ― 涙と笑いの中に、“生きる意味”が戻ってきた日 ―
第9話 倉庫で泣いて、また歩いた - ― 崩れていく会社の中で、最後まで“立ち続けた男”がいた ―
第10話 崩れる会社で見た背中 - ― 壊れた会社。社長の信念、部長の意思。今度は俺が立て直す。 ―
第11話 動かない執務室の真ん中で - ― 終わりじゃなかった。継がれた熱が、俺を動かした。 ―
第12話 折れた光をもう一度灯す - ― 全てを燃やして。 ―
第13話 光に還るまでの物語 - ― 無音の中に、“おかえり”が聞こえた。 ―
第14話 無音の帰り道
スピンオフ作品
- ― これは、「異世界に行けなかった俺の半生。」の もう一つの世界線の物語 ―
異世界に「転生した」俺の半生。第1話【再会編】もう一度、母に会えた朝。